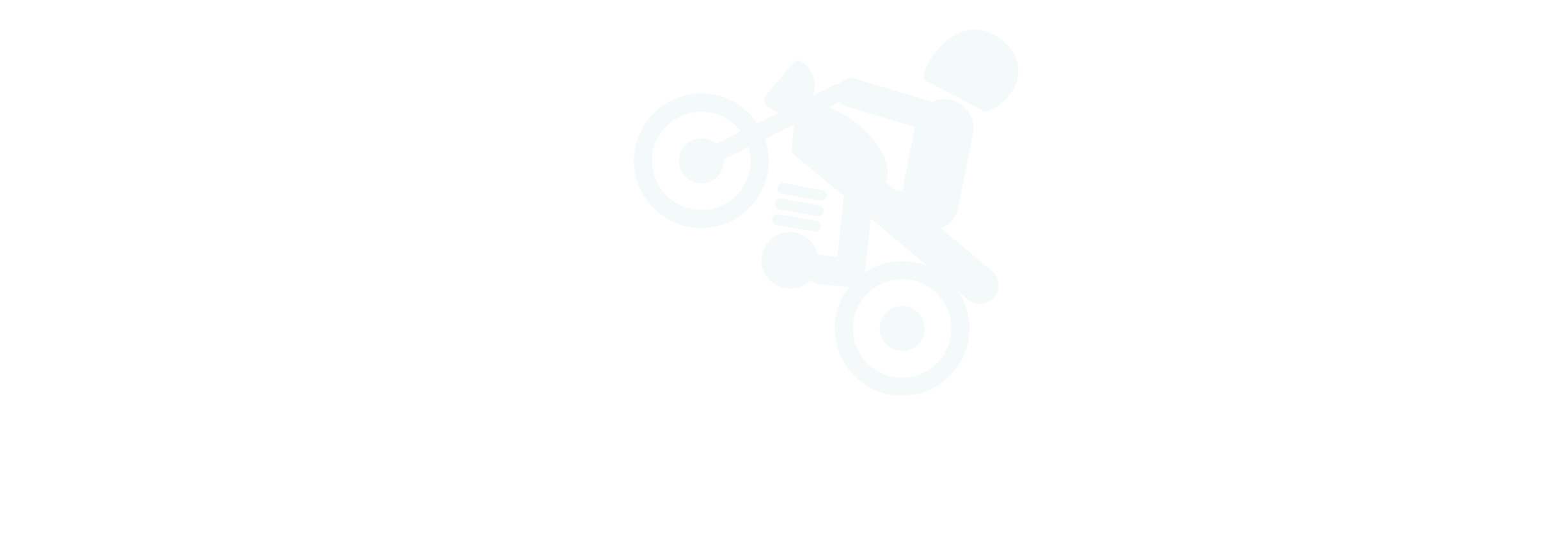初めてインドを旅することになった。
僕には、どうしても外せない、二つの目的があった。
ひとつはヒンドゥー教の聖地バラナシを訪れること。
そしてもうひとつは、コルカタにある、
マザーテレサが建てた「死を待つ人の家」に行き、
ボランティア活動をしてみたかった。
僕を乗せた飛行機がインドに着陸し、空港から出ると、
インド人たちがズラリと並んでいた。
そして、あっという間にヘンな日本語を話すインド人に取り囲まれる。
空港で日本人に話してかけてくるやつは、全員もれなくぼったくりだ。
これはインドに限らず、全世界共通して言えること。
ぼったくりを振り払い、マザーテレサに会うべく、コルカタの街へと向かった
カースト制度はなくなったのか?
公には、カースト制度は、50年以上前に廃止されているが、未だにその影響は根強い。
ダリット不可触民は、不浄の処理(死、血、排泄などに関わる職)を伝統的に担ってきた
存在として、接触すら忌避される。
そして、ダリットとしての身分は、親から子へと世襲的に受け継がれる。
生まれた時から、親がダリットであれば、子供もダリットになってしまうのだ。
ただひたすらに、インド社会の奥底に横たわっているのだ。
何だかやるせない話だが、紛れもない事実である。
生を受けた時から、その生を終える時のことが決まっているのだ。
日本では、やる気さえあれば、なんにだって挑戦することができる。
僕がこうして旅ができることを、とても幸せに感じると同時に、
周りを気にしすぎて身動きがとれない日本人を見ると、
「窮屈な国だな」とも思うが、
それでも自由というものが公に認められているだけ、ずっと幸せなことである。
「死を待つ人の家」とは
マザーテレサのことを初めて知ったのは、果たしてどこの国だっただろうか。
ドミトリーにマザーテレサにまつわる本があり、
何気なく読んでいたことがきっかけだった。
その本に、こう書かれていた。
人間にとってもっとも悲しむべきことは、病気でも貧乏でもない。
自分はこの世に不要な人間なのだと思い込むことだ。
マザー・テレサ
コルカタには、今も昔も、沢山の路上生活者で溢れかえっている。
彼らの存在を必要としている人など当然なく、ただ道端でうずくまっている。
これが、マザーテレサの言う『不幸』なのだろう。
死を待つ人の家の活動は、
そうした路上に溢れかえる、今にも死にそうな路上生活者を担架で運んできて、
その最期を看取るというものだ。

この施設には、毎日多くの人が運び込まれては、その人生の最期を迎え旅立っていく。
中には、元気になって施設を出ていく人もいた。
ボランティア内容は、朝の礼拝を受けた後、衣類洗濯をしてから入浴介助、食事介助など。
特にシスターからの指示はなく、皆が各々できることを、自主的に行っている。
午前中に身のまわりのお世話や、簡単な食事を済ませると、
午後は、施設で暮らす人の話に耳を傾けたり、痛い所をさすったりと、
その人に寄り添うようなことが多かった。
死を待つ人の家では、ただ看取ることしかしない。
治療などしないし、それが目的ではない。
とにかく安らかに死んでいけるよう、みんなで看取る。
ただそれだけである。
「してあげる」のか「させてもらう」のか
毎朝の礼拝で、決まって次のように言われる。
「皆さんはここに手助けに来ているのではありません。
これから神に召される方々から喜びを受けに来ているのです」
その当時、施設に日本人のシスターがいて、色々と解らないことを親切に教えてくれた。
このシスターの存在が無ければ、
ここでの体験も、無味乾燥なものに終わっていたかもしれない。
2ヶ月間、この施設でボランティアをしていたが、
その間、数えきれない程沢山の人の最期を見送った。
それでも尚、「死」というものに慣れることはなかった。
看取るとき、手を握り、じっと眼を見ながら寄り添っていると、
言葉は通じないけれど、その瞳の奥に、その人の人生が見えるような気がした。
たぶん悲しいこともたくさんあったはずだ。
それでも私には「サンキュー、サンキュー」と言ってくれて、涙を流してくれる。
こんな僕でも役に立てたのかなと思うと、すごく嬉しくて、泣けてきたことを覚えている。
「皆さんはここに手助けに来ているのではありません。
これから神に召される方々から喜びを受けに来ているのです」
この言葉の意味が、少しわかったような気がした。
大変貴重な2ヶ月間であった。
一生忘れられない、素晴らしい経験ができたと思う。